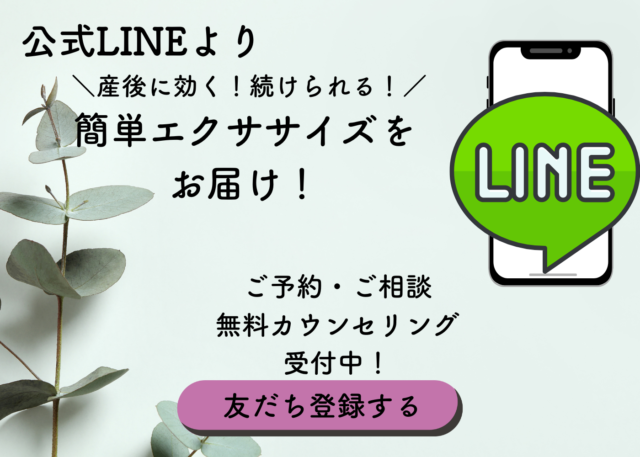自分で”決める”ことが幸せへの第一歩
すべての原因は骨盤のせい?
産後は何年たっても産後です♪
妊娠中から産後 すべての女性が 前向きに過ごせますように✨
土岐市瑞浪市多治見市可児市を中心に 訪問整体を行っておりますヒサコです😊
「自分で決める力」が自己肯定感を育む—子どもの選択を尊重していますか?
好きなもの選んでいいよ~といいつつ
親が「こっちのほうがいいんじゃない?」と無意識にアドバイスしてしまうことはありませんか? 😂
もちろん、子どもが困っているときに手を差し伸べるのは大事ですが、
子どもは「自分で決められない」「親の言う通りにしないといけない」と感じ、自信を失ってしまうこともあります。
ワタシがそうで
「ほら~、お母さんの言うとおりだった」とよくいわれていたので
ワタシがやることは全部だめなんだと思っていたんです。
なぜ「自分で決めること」が大事なのか?
1. 自己肯定感が高まる
「自分で決めた!」という経験は、「自分はできる」「自分の考えは尊重される」という気持ちにつながるのだそう。
小さな決定の積み重ねが、自信や自己肯定感を育みます。
これは子供に限らず、大人でも同様なのだそうで
レシピサイトをみて そのまま料理を作るのと
自分の感覚で自分で「おおさじ1」と決めて作ったときに おいしくできた ほうが
うれしかったりしませんか?✨
こんな小さなことでも 大切なんだそうですよ♡
2. 責任感が身につく
自分で選んだことには責任が生まれます。
成功すれば「自分の選択が正しかった」と自信になり、もし失敗しても「次はこうしよう」と学ぶ機会になります。
3. 自立心が育つ
親に頼らずに自分で考える力がつくと、将来自分で道を切り開く力になります。子ども時代に「決める力」を養うことは、大人になってからの自己判断力にも影響します。
ついやってしまう「親の決めつけ」
子どものためを思ってつい言ってしまうこと、ありませんか?
☑ 「こっちの服のほうがいいんじゃない?」
☑ 「この習い事のほうが将来役に立つよ」
☑ 「これを食べたほうがいいよ」
これらは一見、アドバイスのようですが、子どもの「自分で決める」機会を奪ってしまうことがあります。
子どもが決めたことで失敗したとしても
それは「経験。」
人生の中で 失敗なんてないんです✨
子どもの「決める力」を育むには?
① 選択肢を与える
いきなり「なんでも好きにしていいよ」と言われても、子どもは困ってしまいます。そこで、「AとBのどっちがいい?」と選択肢を提示すると、考える練習になります。
例:
❌「この服にしなさい」
⭕「赤い服と青い服、どっちがいい?」
② 決定を尊重する
子どもが自分で決めたことを、なるべく尊重しましょう。たとえ親の意見と違っても、「いいね!」「それも面白そうだね」と肯定的な反応をすると、子どもは「自分の考えを大事にしてもいいんだ」と感じます。
③ 失敗を責めない
子どもが自分で選んで失敗したとき、「だから言ったでしょ!」と言ってしまうと、自分で決めることを怖がるようになります。失敗も学びのチャンスと捉え、「どうしたら次はうまくいくかな?」と一緒に考える姿勢が大切です。
・・・まさに ワタシですね(´;ω;`)
自分で選んだんだからやるぞ! というパワーがわいてこず
これで失敗したくないから できるくらいのところで終わっておこう
他の人から OK もらえるように動こう
と
他人の目を気にしたり
ある程度のところで 守りに入ってしまうことがあります💦
子どもの自己肯定感を育てるには、「自分で決める」経験がとても重要なんだそうです✨。親が代わりに決めるのではなく、選択肢を与え、決定を尊重し、失敗しても責めずに見守ることが大切ですね。
子どもが自分で考え、選び、行動する機会を増やしていきましょう!
そして、失敗を恐れず 自分はやれる! という気持ちを
たっぷりに蓄えた大人になってもらえるサポートがしたいなと思います✨
あなたは最近、お子さんに「どっちがいい?」と聞いていますか? 😊